
地方裁判所判事
 弁護士
弁護士
大審院判事
飾り刺繍の色と桐花の数で
身分と所属裁判所がわかります。

裁判所書記
胸の唐草と帽子の雲紋がありません。
 検事
検事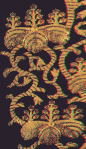
勅任官大礼服
胸飾の桐唐草
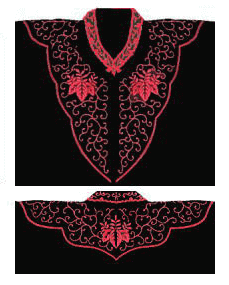
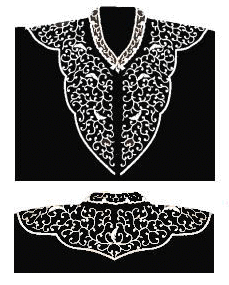
明治時代は日本の歴史上最大の転換期で、服装にも短期間に大きな変化がもたらされました。
草創期の王政復古から欧米礼賛の時代を経て、反動としての日本主義が台頭しました。
和魂洋才、日本の伝統と欧米流の実用性を折衷した、この時期に生まれたふたつの服制、異形の装束をご紹介しましょう。
参考:『法令全書』(内閣官報局 1912)
 地方裁判所判事 |
 弁護士 弁護士 |
 大審院判事 飾り刺繍の色と桐花の数で 身分と所属裁判所がわかります。 |
 裁判所書記 胸の唐草と帽子の雲紋がありません。 |
 検事 検事 |
|||
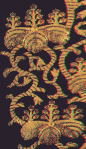 勅任官大礼服 胸飾の桐唐草 |
|||
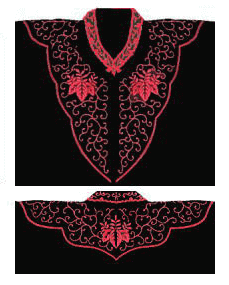 |
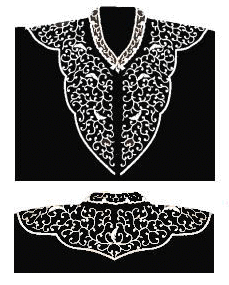 |
||
| 地方裁判所検事法服の詳細 | 弁護士法服の詳細 | ||
近代国家には司法制度の確立が不可欠です。明治元年、太政官に「刑法官」を置いたのを皮切りに、さまざまな変遷を経ました。服制としては特に定めはなく、法曹界の人間は各自で自由な衣服を着ていましたが、諸外国の法服(裁判官などの服)にならい、法服の制度の根拠となる「裁判所構成法」が明治23(1890)年2月10日に公布され、同年11月1日より施行されました。
「裁判所構成法」(明治23年法律第6号)
第百十四条 判事検事及裁判所書記ハ公開シタル法廷ニ於テハ一定ノ制服ヲ著ス
2 前項ノ開廷ニ於テ審問ニ参与スル弁護士モ亦一定ノ職服ヲ著スルコトヲ要ス
さて、こうして法的根拠を得た法服(制服)ですが、ヨーロッパ諸国の法曹は、古くらの伝統衣装を身にまとって法廷の威厳を保っていました。また人を裁く立場の人間は、個人ではなく公人であることを端的に示す必要もあります。当時の司法卿山田顕義は、ヨーロッパ諸国同じような法服を日本の裁判所でもと考え、東京美術学校(現:東京芸術大学)教授の黒川真頼に新しい法服の考案を依頼しました。この法服は法廷の荘重さと法曹の威厳を示すために聖徳太子とされた図像を土台とし、ヨーロッパの法服を参考にして、文官大礼服における装飾を加味し、和洋折衷の独特なものとなりました。
こうして「裁判所構成法」に基づき、判事(裁判官)、検事(検察官)、裁判所書記の制服が、明治23年10月22日勅令をもって定められました。
「判事検事裁判所書記及執達吏制服ノ件」(明治23年勅令260号)
判事、検事、裁判所書記及執達吏制服左ノ図表ノ通定ム
但明治二十三年十二月三十一日迄ハ「フロックコート」又ハ羽織袴ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得。
ここに「雛形」として図示されているものの一部をご紹介します。なお、裁判に関与しない執達吏の制服は、いわゆる法服ではなく、警察官に似た洋服でした。
| 第一図第二図 (大審院判事検事) |
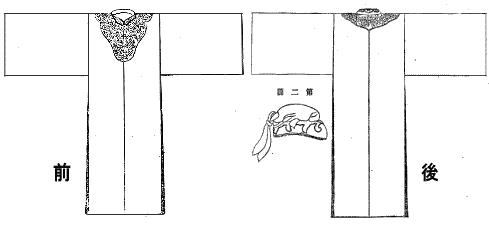 |
| 第七図第八図 (書記) |
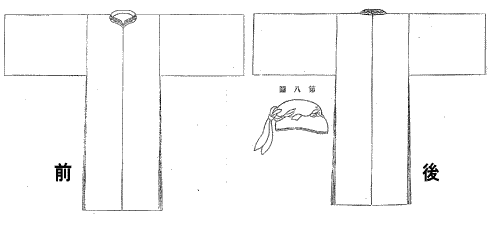 |
通常の洋服の上に上衣をまとい、帽子をかぶるタイプで、上衣は広袖、縫腋の袍のようで脇には襞があります。色は黒、特に生地の地質は定められませんでした。黒は「他の色に染まらない」中立性を表したとも言われていますが、それは恐らく後付の理由でしょう。当時の官員の制服がほとんど黒を地質としていたことのほか、高位装束の黒袍に影響されたことも想像されます。肩から胸部、後ろ襟にかけて唐草模様の刺繍があって、それにより役割と身分を示しています。深紫が判事、深緋が検事というのは律令の位当色から来ている色遣いでしょう。「濃」ではなく「深」を用いていることに、考案者黒川真頼の奈良朝好みがわかります。帽子は黒地に黒糸で雲形紋を刺繍したもので、区別はありませんでした。これも装束の冠を思わせます。
書記の法服は胸の飾りが無く、襟の唐草のみで、刺繍の色は深緑でした。 深紫>深緋>深緑の色の序列は、まさに律令の位当色そのままです。また帽子に雲紋の飾りがありません。ちょうど装束における冠の「遠文」のようで、雲紋のある判検事が五位以上、書記が六位以下に相当するような序列にあったと言って良いでしょう。
弁護士の職服は3年遅れて明治26年に制定され、判事・検事にある桐花がありません。桐花は皇室の文であり、官吏を表す標章でもありました。判事と検事が同じ側の衣服であるのは、今日と裁判制度が異なるためです。「職権主義」と呼ばれた戦前の法廷においては、判事をはさんで(向かって)左に検事、右に書記が、壇上横並びに着席するという形式で、弁護士は一段低い右手の席に着席するというものでした。ちなみに現在は「当事者主義」と呼ばれ、法服を着た裁判官のみが壇上に上がり、下段左右に平服の検察官と弁護士が対峙する形式となっています。
こうした法服は形式だけが規定されたもので、陸海軍将校の軍服と同じく官給ではなく、法官各自がオーダーして誂えたものです。貧しい判事の妻が自ら仕立て、胸飾りを刺繍して拵えた、というような美談も残っています。
貫頭衣のように頭から被る形式や、前開きとして隠しボタンで止めるように改良されたもの、あるいは表にボタンが見えるものなどもあり、かなり自由であったようです。弁護士会には共用の法服もありました。
この法服は昭和22年4月に「裁判所構成法」が廃止されて根拠を失いましたが、新しい「裁判所法」に制服の定めがなかったため、その後も任意で着用していた判検事・弁護士もいたようです。その後、昭和24年に最高裁判所が「裁判官の制服に関する規則」を定め、旧法服は姿を消し、現在の完全にアメリカ式のガウン風の法服が用いられるようになりました。
判事・検事・書記制服 (明治23年10月22日勅令260号)
| 大審院 | 控訴院 | 地方および区裁判所 | ||
| 判事 | 上衣 | 地質:黒地 飾:桐花七箇及唐草 深紫 |
地質:黒地 飾:桐花五箇及唐草 深紫 |
地質:黒地 飾:桐花三箇及唐草 深紫 |
| 帽 | 地質:黒地 飾: 雲紋 |
|||
| 検事 | 上衣 | 地質:黒地 飾:桐花七箇及唐草 深緋 |
地質:黒地 飾:桐花五箇及唐草 深緋 |
地質:黒地 飾:桐花三箇及唐草 深緋 |
| 帽 | 地質:黒地 飾: 雲紋 |
|||
| 書記 | 上衣 | 地質:黒地 襟飾:唐草 深緑 |
||
| 帽 | 地質:黒地 | |||
| 弁護士 | 上衣 | 黒 唐草白糸をもって縫着す | ||
| 帽 | 黒 雲文黒糸をもって縫着す | |||
弁護士の職服は司法省第4号(明治26年4月5日)によります。
大審院は今日の最高裁判所、控訴院は高等裁判所に相当します。
 東京美術学校教員(教諭)
東京美術学校教員(教諭) 
明治初期の極端な欧米礼賛は「鹿鳴館時代」になると次第に反感を招きました。
官立の美術学校である「東京美術学校」は、まず日本固有の美術の振興を目指して明治18年、文部省に「図画取調掛」が設置され、フェノロサ、岡倉覚三(天心)、狩野芳崖らが委員となって設立の準備を始めました。そして明治22年2月、普通科(2年)、専修科(3年)、特別の課程(1年)を置いた五年制の学校として発足しました。第一期生は65名でした。
初代校長は浜尾新、主席教授は橋本雅邦でしたが、実務を仕切っていたのは岡倉天心で、制服を定めたのも彼です。東京美術学校が「我が国固有の美術の振興」を目的としたこともあり、岡倉天心の反鹿鳴館思想もあって、その制服ははるか奈良時代の朝服を彷彿とさせる特異なものとなりました。実質のデザインをしたのは、風俗史の教授であった黒川真頼とされています。そう、上記の法服をデザインしたのと同一人物です。
上衣は、武官の闕腋袍(ただし茨城大学保存の遺物を見ると、当帯の上までは縫われています)を筒袖にしたもので、袖口を括れるようになっています。袴は表袴のような筒袴で、同じように足首で括って実用性を高めており、武官の履き物である麻鞋(麻の糸靴)を履いていました。伝統と同時に活動性の良さを追究したものでしょう。第一期生の卒業記念写真を見ますと、裾の長さは人それぞれで、着席しても床に付きそうなもの、膝上のもの、さまざまです。教官は葡萄(えび)色の綾羅紗製、学生は黒の羅紗製でした。帽子は奈良時代の2本の纓のある冠を基本モチーフとして、侍の折烏帽子のように縁がはっきりとした独特のものでした。
この制服の御披露目は憲法発布記念式(明治22年2月11日)で、上野の山から皇居まで、教員・学生が隊列を組み、錦旗をひるがえして行進して人々の注目を受けました。朝鮮の人と思ったり、上野に神主学校が出来たと誤解する人もいたと言うことです。
せっかくの制服でしたが、一部の教官以外には大変不評で、学校の近所に制服を預けて、通勤には平服を用いる教官が続出。周囲の目も奇異と嘲笑をもってされてしまい、天心に招かれて教諭となった彫刻家、高村光雲も「あの制服には困った」と後年述懐しています。学生にも不評でした。しかし当の岡倉天心はこの制服が大のお気に入りで、この服を着てしなやかなアザラシの毛皮の靴を履き、愛馬「若草」にまたがって、颯爽と大学に通勤しました。第一期生卒業の集合写真では、教職員・学生共にこの制服を着用しています。
明治23年の「第三回内国勧業博覧会」開会式では、大礼服の高等官に混じって制服を着た岡倉天心は人々の注目を受け、「いわゆる美術服、折衷服を知らない出品者たちは、袖を引き合ってひそひそと噂した」と当時の新聞の書かれています。
 「若草」馬上の岡倉天心
「若草」馬上の岡倉天心
東京美術学校はその後、時代と共にその目的が徐々に変化し、明治29年に西洋画科が設立されるにいたり、この制服は有名無実のものとなりました。
東京藝術大学に残る銅像
平櫛田中(ひらぐしでんちゅう)作の岡倉天心座像では美校制服がよくわかりますが、この装束は文官式の「縫腋袍」のようにも見えます。ただし襴は見られません。第一回卒業式の写真ではこのように前の合わせが開いておらず、闕腋袍を思わせます。上衣の袖や袴の裾を括ってはいません。
 |
 |
 |
| 岡倉天心(平櫛田中作) | 同右側 | 同左側 |
 |
 |
 |
| 岡倉天心 頭部 |
教授胸像 袈裟懸けに蜷結? |
同背部 冠と纓 |
東京美術学校の制服と、判検事の法服を考案したのが同じ黒川真頼であったため、両者には共通点が多く見られます。そのため、次のような逸話が残っています。
ある事件の証人として東京地方裁判所に呼び出された美校教諭、黒川博士は教官服を着用して早めに裁判所に出かけました。すると裁判所の係員が「まだ開廷には時間がありますから」と、立派な椅子に博士を座らせました。
やがて開廷の時刻に判事たちがやってきてビックリ。判事席に妖しい服装の老人が座っているではありませんか!「どうしましたか」と問いただすと老人は事の次第を説明。判事らは苦笑して「ここは判事席なので証人はあちらへ」と促しました。博士も事情を飲み込んで笑いながら証人席に着席しました。
これは係員が美術学校教官服の博士を早起きの老法官と勘違いしたもので、博士は帰宅後「今日は黒川判事になった」と笑ったそうです。
こうした明治期の「擬装束」は、欧米一辺倒であった世の中の軽佻浮薄さに対する反骨の精神の表れとも言えるでしょう。
今日の目で見ますと(美校制服は当時としても)珍妙なものに感じられますが、時代の流れの中でいかに日本の心を残そうと努力をしたか、そうした気骨を持った明治人、黒川真頼という人物の気持ちを理解すべきなのでしょう。
黒川 真頼(くろかわ まより) 1829(文政12)〜1906(明治39)
幕末の国学者、明治期の歴史・美術史・有職故実研究の泰斗。号は荻園。
桐生出身。旧姓金子、幼名は嘉吉。
幼くして江戸の国学者黒川春村の弟子となり、のちに師家黒川を継いだ。歴史や文学、美術、工芸の実証的研究を深めて明治初期の国史学界をリード、明治11年に文部省から文学博士号を受けた。『古事類苑』編纂委員、東京美術学校・東京音楽学校教授、帝室博物館監査委員などを歴任。
英語の"FineArt"の訳語を「美術」としたのも黒川だと言われ(1873(明治6)年ウィーン万国博覧会出品規定が初出)、また、文部大臣森有礼が構想を持った英語を国語として採用する論(1872)を痛烈に批判し、日本語を守った「言語文字改革ノ説ノ弁」を著したことでも有名。唱歌「天長節」の作詞者としても知られている。著書は『工芸志料』『黒川真頼全集』など多数。