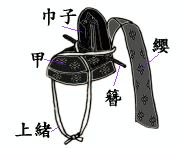
冠は宮中に出入りする官人の公式のかぶり物でした。原則として宮中では冠が不可欠で、天皇も烏帽子をかぶることは許されませんでした。
冠は纓(えい)が下に垂れる「垂纓冠」と巻き込む「巻纓冠」の2種があります。前者は文官用、後者は武官の束帯用です。武官と言えども衣冠や冠直衣の場合は垂纓冠を用いました。また闕腋袍を着る場合でも、警護の任務がない勅使などの際には、垂纓を用いました。
本来「冠下(かんむりした)」というちょんまげを巾子に入れ、それを簪で突き刺して固定しました。この当時はこれで冠が頭上に固定できたので、掛緒は必要ありませんでした。
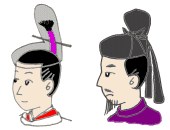
 <冠と烏帽子について詳しくは・・・こちら を御覧下さい。
<冠と烏帽子について詳しくは・・・こちら を御覧下さい。
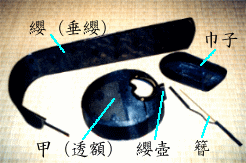
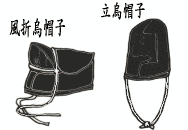
烏帽子は古くは紗、絹などを使って袋状に縫った柔らかな頭巾でしたが、剛装束の時代に堅くなり、やがて現在のように漆で塗り固めたものになりました。表面には「さび」と呼ばれる皺があり、年齢と共に粗くなるのが通例です。
図の左は頭頂部を折った「風折烏帽子」、右は「立烏帽子」です。風折は布衣の際に用い、立は狩衣や直衣に用いました。
掛緒は紙捻が一般ですが、衣冠の冠同様に組み紐を用いることもありました。また蹴鞠の上達によってそれを理由に勅許を受けて組み紐を用いることがありました。四十歳以前は紫、以後は薄色(薄紫)、五十以後は紺色などとされています。現在の神官はいかなる場合でも紙捻を用います。

笏は、中国において、役人が君命の内容を、忘れないようにメモを書いておくための板「手板」であったと言われています。日本においては、笏に必要事項を書き記した紙「笏紙」を裏面に貼って用いていました。のちには威儀を正すために右手に持つ小道具となり、束帯の時および神事に際して用いられました。
律令の定めでは五位以上は象牙製の牙笏(げしゃく)ですが、日本では入手が困難なため、今はすべて木製です。櫟(いちい)が一般的で、そのほか椎、樫などでつくられています。
臣下は上円下円が通常用です。ただし慶賀(祝い事)の場合には「慶賀の笏」と称して、上方下円タイプを用いました。
天皇は上方下方が通常用。神事に際しては上円下方タイプを用いました。
笏の寸法
記録には「長さ1尺2寸、上広2寸7分、下広2寸4分、厚3分」などとありますが、持つ個人差や家々による流儀の違いもあり、まちまちです。
通常用
慶賀用
通常用
神事用


もっとも一般的な櫟(いちい)は「一位」に通じるとされて、ポピュラーです。飛騨国の位山産のものが最上とされました。その他「ふくら」(モチノキ)も用いられ、天皇は「ふくら」を用います。
古くから「板目が良く、柾目は良くない」とされてきました。その理由は明らかではありませんが、笏を楽器として打ち合わせる「笏拍子」をとるときに、柾目だと割れやすいということも理由の一つと考えられます。

平安時代の中期から用いられたもので、笏だけではメモ欄が少ないという理由からか、薄い檜板を糸で綴って扇の形にしたものです。これは日本独自の物です。
束帯、衣冠など冠を着用する場合には必ず用いました。ただし束帯の場合は懐中するだけのもので、衣冠の場合は笏を持たないのでこれを笏の代わりに右手に持つことになりました。狩衣でも冬場は持つことがあります。
糸綴じの端には白絹布で家紋などを貼り付けます。これを「置文」と呼びます。また若年ではこの家紋の下に糸で模様を付けたりしたものです。板は「橋」と言い、かつては公卿が25橋、殿上人が23橋でしたが、現在は25橋が一般的です。

蝙蝠は夏の持ち物で、直衣や狩衣の際に用いました。この目的は現在の扇子とほぼ同じで、酷暑冷却用のものです。今日の扇子と異なるのは骨が5本程度と少ないこと、骨の片面しか紙が張られていないことです。かつての宮中での蔵人などの活動的廷臣は冬の束帯でも檜扇でなくこれを用いたそうです。
非常に軽便なために多用されました。

室町時代後期ごろから用いられたとされる扇で、衣冠や直衣の際に用いられました。檜扇では儀式張りすぎるということでしょう。主に冬に用いられましたが、夏には夏扇という現在の扇子に似た先が広がっていないもの(下の「ぼんぼり」)を利用したためらしいです。中啓とは中ぐらいに啓(ひら)いた扇ということで、もっと先端が広いた扇を「末広の扇」と呼びます。
中啓と扇の中間格で、今では女子装束の袿袴の際に持ちます。普通に見られる先の閉じた扇子は「鎭折(しずめおり)の扇」と呼ばれます。

さまざまな用をなす懐紙が儀礼用に変化したもので、束帯や衣冠の際に懐中します。束帯の場合は単色ですが、衣冠の場合は二枚の色を変えて重ね色目を楽しみました。
現在は白の檀紙または鳥の子紙を用い、若年は紅の鳥の子、壮年は白の檀紙に金箔を散らしたもの(写真)、宿老は白の檀紙を用いるようになっています。

浅沓は文官の束帯、衣冠以下装束着用時に履くものです。武官の束帯は靴の沓(かのくつ)と呼ばれる革ブーツを用い、文官でも雨天時には深沓と呼ばれる革製の長靴を履きましたが、通常は浅沓が用いられました。
堅い沓なので足の当たりを和らげるクッションとして「込」「甲当」と呼ばれるものを白平絹で作って取り付けてあります。また靴の中敷きには「沓敷」が貼られますが、これは束帯の表袴の裂地を用います。ですから皇族は「かに霰」臣下四位までは「八藤丸紋」(写真)、五位以下は白の平絹です。
浅沓は張貫(はりぬき)製、底は桐板です。張貫とは、木型の上に和紙を何枚も張って「ふのり」で固めて木型からはずし、表面を漆塗りで仕上げた「はりぼて」で紙製とは思えない強度があります。プラスチック製ゴム底の普及品もあります。

武官の束帯専用のように考えられがちですが、束帯の場合は文官でも正式にはこれを履きます。上部の牡丹錦の部分の地が赤なのは公卿、青は殿上人用です。本体は皮に漆を塗ったもので、表袴の裾を錦の中に入れ込んで履きます。
靴の内張は花菱紋の白綾です。
この靴を履く場合に限って靴擦れ防止のため「襪(しとうず)」という指股のない足袋を履きます。ですからこの靴を履かない衣冠・直衣・狩衣の場合は素足が原則となります。

律令の「烏革履(くりかわのくつ)」を思わせる皮を黒塗りにした靴です。浅沓のように白の甲当てと沓敷きがあります。革靴ですからとても軽快で便利ですので、現在宮中で侍従や掌典(神事担当者)が履いています。鎌倉時代頃に描かれた公卿の履いている沓は浅沓のようですが今のように甲が巨大ではなく、折れ曲がっている図もありますから、烏皮履のようなものであったのでしょう。

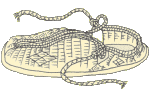
糸を編んで作ったズック靴のような履き物で、菱模様を編み出し、底は革製です。もともと六位の武官の履き物でした。その頃は麻製(麻鞋・まかい)でしたが今は儀式用なので白絹糸で編みます。半尻、童形束帯など子ども、未成年者が着用します。皇族の成人式において袍(子どもは闕腋袍)にこれを履きます。また地鎮祭に奉仕する童女が汗衫にこれを履きます。
図のようにまるでズックです。足を入れたら紐を足首に2度回して、前で諸鉤に結びます。図では煩雑になるため紐を短く描いていますが、実際にはもっと長いものです。