

白鳳時代の冠
闕腋袍の武官装束のため纓は巻纓です
典型的な室町時代の剛装束姿
冠もすっかり堅いものになっています
古墳の埴輪で判るように、ハット形式の帽子は古くから存在していましたが、朝廷に属する官人が制帽として冠をつけるようになったのは聖徳太子の冠位十二階制が出来てからと考えられています。こうしたステータスシンボルから出発した被り物着用は、やがて成人男子の証(あかし)と言えるような存在になりました。平安時代には庶民(京畿在住者だけでしょうが)に至るまで頭に被り物をつけ、露頂を恥とする文化が生まれたのです。
冠は朝廷に出仕するときの公式ユニフォームに附属する帽子です。天皇は常時宮中にいるので、常に冠であり、烏帽子を着用できるのは退位して上皇となってからのことでした。
奈良時代の律令では冠は「頭巾(ときん)」と呼ばれるもので、羅や縵(かとり)という薄い布の袋でした。これには4本の足がついていて、前2本で頭頂部を覆って結び、後ろ2本で冠の上から髻(もとどり・いわゆるチョンマゲ)を結んで固定し、余りを後ろに長く垂れ下げました。
 |
 |
| 伝 聖徳太子像の頭巾 白鳳時代の冠 闕腋袍の武官装束のため纓は巻纓です |
伝 源頼朝像 典型的な室町時代の剛装束姿 冠もすっかり堅いものになっています |
その後、奈良を経て平安中期までは、この形式の柔らかい袋状の冠を用いていたと考えられています。それが漆で固めて巾子(こじ)をしっかりと形作った冠になるのは、摂関期の頃ではなかったかと考えられていますが確証はありません。院政期の剛装束化で漆塗りが強化されてしっかりとした冠になりました。
現代の冠は張貫(はりぬき)の上に羅(ら・うすい絹)を張っています。張貫とは、木型の上に和紙を何枚も張って「ふのり」で固めて木型からはずし、表面を漆塗りで仕上げた「はりぼて」です。紙製とは思えない強度があります。
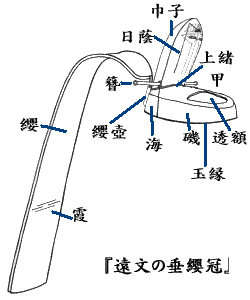 |
冠の名所(などころ) 頭に乗せる部分の前の方を「甲」または「額」と呼ばれます。ここに穴を開けて熱気を逃がしたのが「透額(すきびたい)」で、現在の冠はほとんど透額になっています。もちろんこの上に羅を張りますので穴は覆われます。 後ろに高くそびえるのが「巾子(こじ)」です。古くはここに髻(もとどり)を入れて、左右から「簪(かんざし)」を差し貫いて冠を固定しました。簪は角(つの)、笄(こうがい)とも呼びます。 摂関期は、纓は纓壺なしで、いきなり巾子から下に垂れていたのではないかと考えられます(源氏物語絵巻など)。その後、院政期に強装束が流行しますと纓壺を作り、そこに纓を差し込んで一度上に上がって垂れる形式になりました。簪も左右から差す形ではなく、片方から一本差し貫く形式的なものとなりました。 甲の部分は厚紙に漆を塗った型枠に羅を張って漆塗り、巾子は中空の紙製型枠に羅に張って漆塗り、纓は古くは鯨のひげ、今日では樹脂で枠を作って羅を張ります。 |
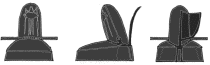 |
冠を3方向から見た図 |
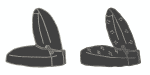 |
磯高の冠 近年の冠の縁は前の「磯」よりも後ろの「海」が高いタイプ(図左)ですが、勧修寺(かじゅうじ)家は東大寺型という独特の冠(図右)を使いました。磯が海より高いので、「磯高の冠」と呼びます。 |
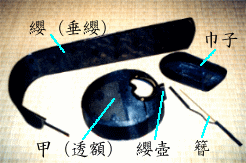 |
放巾子の冠 冠は本来固定したものですが、近年のものは使用持ち運びの便を図って分解式のものが主流になっています。これは、甲の部分、巾子、簪、纓がそれぞれバラバラになります。こうした冠を古くは「放巾子(はなちこじ)」と称し、特に加冠(成人式)に用いました。組み立てる場合は甲に巾子を差し込み、横から簪で突き刺し固定します。さらに纓壺に纓を差し込んで完成です。 |
律令の定めでは、五位以上が有文の羅、六位以下が無文の縵で頭巾を作ることになっていました。のちに冠として形式化された平安時代にも、五位以上の冠には文がほどこされ、六位以下は無文でした。これは「文羅」という特殊な織り方で作られた文様です。
しかし応仁の乱でこうした「文羅」を作る技術知識が失われてしまい、巾子1か所と纓の下部に唐花菱を模した4本の線(これを「霞(かすみ)」と呼びます)を刺繍して「有文」としていました。ですからこの当時の絵画における冠は高位の者でも無文に見えます。
江戸時代、貞享4(1687)年の大嘗祭に、文羅ではなく刺繍で冠全体に模様を施す形式で冠の文が復活しました。
五位以上の纓と甲には合計31または33の紋が刺繍されます。これを「繁紋冠(しげもんのかんむり)」と言い、五摂家でそれぞれの定紋がありました。公家は自分が属する門流の文を用い、天皇さえも冠親となった摂家の文を用いましたが、公卿でも摂家の門流とならない清華家や源氏などはそれまでの霞文(遠文)冠を用い、藤原氏でも独自の動きをしていた「勧修寺(かじゅうじ)家」流は、太めの横線四本で菱を模した図柄を全体に散りばめました。勧修寺家は代々蔵人・弁官や摂関家の家司として日記をつけ、そこから故実を引用することを家の職能としていたためか、古式の磯高の冠を用いるなど、独特の「こだわり」を持った家だったようです。
現在では天皇・皇太子の菊花文、宮家の俵菱(摂家に属するわけではないでしょうが)を除き、おおむねすべて横菱(一條家タイプ)になっています。六位縹袍以下の冠は遠文冠(とおもんのかんむり)と言い、復活前の「有文」つまり纓に4本の横線があるのみです。遠文冠は無文冠ではないので注意してください。
なお、繁文冠の菱は甲部分は横菱ですが、一條家・九條家タイプの場合は、纓部分については縦方向の菱にするのが故実です。しかし今日ではあまり意識されずに宮中でも横向きの菱の纓が用いられることもあるようです。
繁文が復活しますと、それまでの略式霞のある有文冠を「遠文冠(とおもんのかんむり)」と呼び、六位以下の料としました。つまり無文冠が一般にはなくなったわけです。現代の神職は二級以上が繁文、三級・四級が遠文です。
無文冠は天皇の神事などで用いられます。逆に神職は凶事の際に用います。
| 摂家門流の羅文 | 他 | ||||
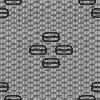 |
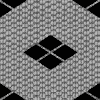 |
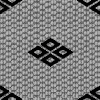 |
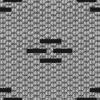 |
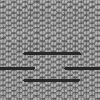 |
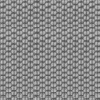 |
| 近衛家 | 一條家 | 九條家 | 勧修寺家 | 門流不属 | 凶事など |
| 繁 文 | 遠文 | 無文 | |||
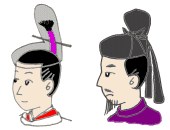
纓は、冠を固定するの簪を使って固定する(図左)平安時代には、単なる飾りになっています。古い頭巾時代の紐で絞った名残で、纓は後々まで二枚で作られています。平安時代には燕尾(えんび)の纓で、左右の肩に垂れ下げるなど、まさに二枚でしたが、剛装束となった平安末期からは、二枚を留めて一枚のようにして用いるようになりました。現在でも二枚を張り合わせた形式です。
冠は纓(えい)が下に垂れる「垂纓冠」と巻き込む「巻纓冠」の2種があります。前者は文官用、後者は武官の束帯用です。武官と言えども衣冠や冠直衣の場合は垂纓冠を用いました。また闕腋袍を着る場合でも、警護の任務がない勅使などの際には、垂纓を用いました。逆に緊急事態であるとか、凶事の際は文武を問わず巻纓にしました。現在の神職は葬儀に際して巻纓を用います。
纓は剛装束の登場時期から今のように、纓壺に入れて一度上がって垂れる形式になったと考えられます。平安末期に描かれたと思われる源氏物語絵巻では纓壺はなく巾子にいきなり纓が付けられているように見えますし、同じ時期に描かれた伴大納言絵詞では纓壺があるようにも見えます。摂関期にどのような冠と纓であったのかは、よく判っていません。
六位の武官がかぶった冠に「細纓(ほそえい・さいえい)」があります。鯨のひげや竹をたわめて黒塗りしたものを2本一組にして纓壺に差し込んだものです。現在では葵祭などの祭儀でわずかに見ることが出来ます。
平安時代までの冠は大きく、頭にすっぽりとかぶせるような形でした。しかし後世のように型枠がなく布に漆塗りですから軽く、簪で留めるだけでずり落ちるものではありませんでした。その後、剛装束となって冠に型枠が入るようになりますと重みも増し、簪だけでは留めることが難しくなってきます。さらに風俗の変遷で室町後期に頭頂に月代(さかやき)を剃るようになりますと、髪の量が減って太い髻を結えなくなると、どうしても掛緒で固定せざるを得なくなりました。留め具で髪に留めて掛緒を掛けて留めますが、そうなりますと小さい方が安定が良いので、江戸時代に冠のサイズはどんどん小さくなってオモチャのようになり、頭の上にちょこんと乗せるようになりました。
明治に入り髷を結わなくなりますと、冠を留める部分が無くなったために、帽子のようにすっぽりとかぶるサイズになりました。これを頭にかぶり、掛緒でしっかりと固定します。
| 職方2家の冠の違い | 冠はかぶる個人に合わせたオーダーメイドです。 装束店には多くの種類の型があり、内のり縦横の寸法から適切な型サイズを選んで制作します。今日、冠づくりの職方は4家(そのなかでも山岡・八幡が多い)あり、磯の傾きや巾子の大きさ、纓壺の付け位置などが微妙に違います。八幡製は巾子が大きく平安風に雅やかで、山岡製は磯の角度が比較的緩傾斜なので、頭へのフィットが良いようです。 |
|
 |
 |
|
| 山岡製 磯の内張 紺ビロード |
八幡製 磯の内張 黒ビロード |
|
束帯の冠の掛緒は和紙でこよりを作って呉粉を塗った「紙捻(こびねり)」を使います。巾子の後ろ纓壺の上に紙捻を当て、巾子の左からまわした方を上にして左右交差させ、下におろしてあご下で結びます。
結びは結切(いわゆる固結び)が本義ですが、近衛家は右片鉤(図中)、九條家は左片鉤を用いました(左右は自分から見たもの)。諸鉤は凶事にのみ用いる結び方です。

衣冠の場合でも紙捻を使う場合は束帯と同様ですが、略儀の装束である衣冠では丸組紐を用いることがありました。これは天皇からの拝領の他、蹴鞠上達により飛鳥井家や難波家から組掛を許され、それを理由として勅許を得れば冠の緒としても使えるようになりました。この場合の結びは一度結切に結び、その後に諸鉤に結んで胸に垂らします。
烏帽子は公家や仕える人たちの日常のかぶり物です。これは平安時代には羅で出来ている袋に漆を塗った丈の高いものでしたが、鎌倉以降次第に高さが低くなり、江戸時代に紙にしわを付けて漆を塗った箱形のものに変化しました。種類はいろいろありますが、基本は公家が一般に用いた「立烏帽子(たてえぼし)」です。
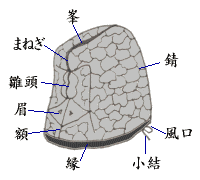 |
立烏帽子の名所 江戸時代以降の立烏帽子の例です。 紙をくしゃくしゃにして漆を掛けたものですが、全体のしわを「錆(さび)」と呼びます。真ん中のつなぎ目が「峯(みね)」、前面に凹みがあり、「雛頭(ひながしら)」というヒョウタンのような突起、その下に「眉(まゆ)」という折り目のような部分があります。これは平安時代の丈の長い烏帽子の時代に前面をへこませた形を形式的したものです。 頭と一番後ろのすき間を「風口(かざくち)」と呼び、「小結(こゆい)」の紐が左右の縁内側についていて、これをしばることで多少サイズの調整が利きます。 |
烏帽子には前面に眉という折り目を作っています。若いときには左右ともに折り目を付けた「諸眉(もろまゆ)」の烏帽子を使いましたが、一般には左眉を用いました。右眉は上皇専用の烏帽子です。ただし上皇から許可を得た家は、代々右眉を用いることが許されました。
現在の神職が狩衣姿でかぶる立烏帽子は諸眉です。
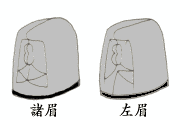 |
| 烏帽子の眉 |
烏帽子の表面の凸凹のしわを「錆(さび)」と呼びます。年齢が高くなるにつれ、また官位が高くなるにつれて錆は大きくしました。従って六位以下の地下がかぶった風折烏帽子は、みな小錆です。
現在の神職の立烏帽子はほとんどが小錆、まれに柳錆を用いているようです。
 |
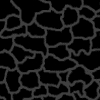 |
 |
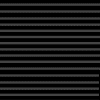 |
| 大錆 | 小錆 | 柳錆 | 横錆 |
 三條実美
三條実美
冠と同じように、烏帽子も時代の流れで大小の変遷があります。江戸時代には写真のような小さな物になり、頭の上にちょこんと乗せました。明治以降は大きくなって頭にすっぽりとかぶります。今日一般には冠と違い、烏帽子はフリーサイズです。風口そばの「小結(こゆい)」の締め具合である程度サイズを調整できます。
 |
 |
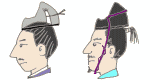 |
| 平安の立烏帽子 | 翁掛 (おきながけ) |
侍烏帽子の 留め方の変遷 |
烏帽子は紐(掛緒)なしでかぶるのが本来の方法でした。この場合、「小結(こゆい)」という内側に付けた紐を髻(もとどり)の根元に結びつけて固定します。烏帽子が薄物の布で出来ていた時代は軽量なので、これだけで十分固定できたのです。室町時代以降は小結の紐は単に飾りに近いものになり、掛緒で留めるようになります。このあたりの推移は冠と同様です。烏帽子の内側左右に乳(ち)の輪を付け、そこに紙捻(こびねり)を通して下に出し、あご下で結びます。この掛緒の掛け方を「忍掛(しのびがけ)」と呼びます。また年齢とTPOに応じて図のような「翁掛(おきながけ)」と呼ばれる、掛緒が完全に表に出る方式も用いました。蹴鞠では常に翁掛です。翁掛は十文字にして後ろにも紐を回す方式もあります(下、風折烏帽子の図参照)。
侍烏帽子の場合、髻(もとどり)に紙捻を結び、烏帽子に穴をあけて外に引き出し、烏帽子後部で烏帽子に結びつけます。この外に出た紐の部分の小結を粋なものとして美意識が生まれ、色を付けたり長くしたりしたのです。普段はこの小結留めだけでしたが、烏帽子がずれてはいけない儀式や出陣の際には、「頂頭掛(ちょうずがけ)」の掛緒を用いてさらに安定させました。室町時代に髪型が変わると小結止めが出来なくなり、頂頭掛を常時使わざるを得なくなりました。
掛緒は紙捻が一般ですが、衣冠の冠同様に組み紐を用いることもありました。また蹴鞠の上達によってそれを理由に勅許を受けて組み紐を用いることがありました。四十歳以前は紫、以後は薄色(薄紫)、五十以後は紺色などとされています。現在の神職(神社本庁)はいかなる場合でも紙捻を用います。
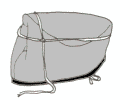 |
 |
 |
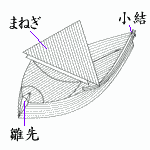 |
| 風折烏帽子 左折り |
古式の 侍烏帽子 |
舟形の 侍烏帽子 |
侍烏帽子の名所 |
立烏帽子からさまざまなバリエーションが生まれました。
風折烏帽子は平安風の高い立烏帽子が動きにじゃまになるので、上部三分の一くらいを折り曲げることがありました。ここから生まれたのが「風折烏帽子(かざおりえぼし)」です。カジュアルな烏帽子として軽快に利用されて、室町時代には上級武士たちも用いました。やがてそれも公式化されて上皇と地下(じげ)が用いるものとされました。上皇用は右折り、地下は左折りが原則(例外あり)です。掛緒は、上皇は組紐も用いましたが、地下は常に紙捻です。
侍烏帽子は立烏帽子を何度も折り畳んで髻(もとどり)を収容する巾子形だけ残したものです。本来は「折烏帽子(おりえぼし)」と言います。折り方は「観世折り」など数多くの流儀がありました。その後室町時代に髪型が変わると巾子形を設ける必要が無くなり、反対に前の方に大きな三角形を作る折り方が流行します。さらに江戸時代にはいると形式化は一層はげしくなり、紙に漆を塗った舟形の侍烏帽子となって下級の侍の礼装である「素襖(すおう)」装束専用のかぶり物になりました。この舟形侍烏帽子は形状が当時の納豆の包装に似ていたために「納豆烏帽子」とも呼ばれます。
今日、相撲の行司は鎧直垂に鎌倉時代のような古式の侍烏帽子をかぶりますが、冠や烏帽子同様に、すっぽりと頭にかぶる帽子状のサイズです。
 |
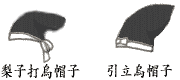 |
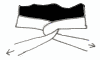 |
| 引立烏帽子 | 萎(もみ)烏帽子の種類 | 鉢巻の引違え |
兜の下につける柔らかい烏帽子を「萎烏帽子(もみえぼし)」と呼びます。これをかぶるときは、白い布で鉢巻きをします。梨打烏帽子は後ろで結び、引立烏帽子は前で結ぶのが特色です。鉢巻きは結ぶ反対側で引き違えます。例えば梨打烏帽子でしたら後ろから始めて前で引き違え、後ろに回して結びます。この引き違えるときは交差させるのではなく、左右をからませて(上右図)後ろに戻します。兜の上部にある「頂辺(てへん)の穴」から烏帽子を引き出し、兜の安定を図りました。
明治草創期、政府に出仕する無位の官吏の礼服として直垂が用いられましたが、その際は梨打烏帽子を用いました。
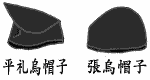 |
| 召具の烏帽子 |
召具と呼ばれる下働きが付ける烏帽子です。退紅(たいこう)や雑色(ぞうしき)が用いたのがごく簡単なつくりの風折烏帽子のような「平礼(へいらい・ひれ)烏帽子」です。さらに下級者である白丁が用いたのが、2枚の薄布を張り合わせただけの「張(はり)烏帽子」です。