HOME>装束の知識と着方>雅なお遊び>双六
平安のヒットゲーム「双六」
平安時代を代表する室内遊戯といえば、まず碁でしょう。そしてより庶民的で流行したものに「双六」があります。
囲碁に関しては用具もルールも現代に伝わっていますので、あえて紹介するまでもありませんが、双六は子供の
お正月遊び「紙双六」に変化してしまって、平安の遊びとは違うものになってしまい、本当の双六「盤双六」は
すたれてしまっています。
ここでは双六のルールをご紹介して、賭事に使われて何度も禁令が出されたほど平安人が熱中した楽しみを
感じていただきたいと思います。
ただし本当の平安時代のルールというのは実は判っていません。「ぞろ目」である「重五」「朱四」などの
さまざまな専門用語が古い記録に残っていますが、それがどういうもので、どういった働きをゲーム中でするのか
今では正確なことは不明です。たぶん「ぞろ目が出ればもう一度賽を振れる」ルールであったでしょうが・・・。
ここでは文献に見られるルールの断片と、同じインド発祥のゲームが変化したと言われる西欧の「バックギャモン」から
推測したルールをご紹介します。
双六の道具
双六盤、白コマ・黒コマ15ずつ、振り筒、サイコロ2個を用います。
振り筒にサイコロを入れて盤にはっしと打ち付ける姿が絵巻物「長谷雄草紙」に描かれています。双六盤は上下
それぞれを12区画に仕切り、中央に分離帯を設けた形で線が引かれています。
ゲームの種類
双六盤をつかったゲームには、「本双六」「柳(つみかえ)」「追い回し」「折り葉」などがあります。どれも基本的なルール
は同じ様なもので、自分の色(白か黒)のコマをすべて自分の陣地に入れたら勝ちです。その中でも最も単純なのが
「柳(つみかえ)」でしょう。なお先手後手は、それぞれが1個ずつ同時にサイコロを投げて数の多かった者が先手になります。
柳(つみかえ)
白黒ともに、端の区画に15コマ積み上げ、これをサイコロの数で前進させて、反対側の端の区画にすべて
入れれば勝ちです。あまりテクニック性のない単純なゲームで、入門には良いでしょう。
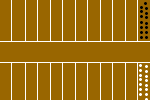 (1)2個のサイコロの目の数だけ2個のコマを前進させても良いし、目の合計数だけ1コマ
(1)2個のサイコロの目の数だけ2個のコマを前進させても良いし、目の合計数だけ1コマ
前進させても良いのです。たとえば出た目が「3」と「5」であれば、2個のコマをそれぞれ4区画、6区画に前進させても
構いませんし、1個のコマを9区画へ前進させても構いません。
(2)ゴールには、ジャストの数の目が出なければ入れません。ます目よりもサイの目が多いときは、その分、ゴール区画
から逆戻りすることになります。たとえば10区画では「2」が出なければゴールできず、「6」が出ればゴールに行って戻り、
8区画にコマを置くことになります。
(3)逆戻りした次の回には、そのコマは再びゴールへ向かって前進する形になります。
本双六
最初に基本形にコマを置き、そこからサイの目に従ってコマを動かし、自分の陣地に自分の色のコマをすべて
入れれば勝ちです。目標は「柳」と同じですが、相手の邪魔をしたり、自己防衛をしたりすることができるゲーム性が
あります。
ルールのポイントは次のとおりです。
・2コマ以上相手のコマがある区画では止まれない
・相手のコマが1つだけある区画で止まると、相手のコマを中央ゾーンへ飛ばすことができる。これを「上げる」と言う
・上げられた側は、次の回にそのコマを振り出しに戻して、そのコマを使った動きをしなければいけない
・相手が2コマ以上いるゾーンへしか動けない状態になったら、その回はパスになる
・一つの区画に何個のコマが入っても構わない(図ではわかりやすく5個までにしていますが)。
説明を文章で読みますとややこしいですが、実際にゲームしてみますとルールはすぐに呑み込めます。
<ゲームの例>
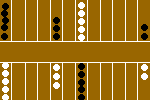 |
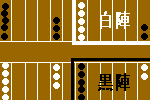 |
| 初期状態の配置 |
両方の陣地の位置 |
(1)この図では黒側に座っていると考えます。黒の陣地は下段の右から1〜6区画のゾーンです。
コマの動かし方は上段は右から左へ、下段に下がって左から右への「反時計回り」になります。白側に座れば
右上がゴールゾーンで、動きは黒とは逆に「時計回り」になります。
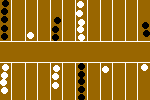 (2)白が先手になったとして、サイコロの目が「3」と「3」が出たとします。進行方向のルール
(2)白が先手になったとして、サイコロの目が「3」と「3」が出たとします。進行方向のルール
さえ守ればどのコマからでも動かせるので、例えば右下端と左下端のコマをそれぞれ3進めました。
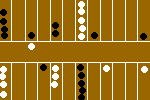 (3)次に黒の番。サイコロは「4」と「2」。まず右上端のコマを4前進させました。そして
(3)次に黒の番。サイコロは「4」と「2」。まず右上端のコマを4前進させました。そして
上段8区画のコマを2進めました。ここに白が1個だけありましたので、これを中央部に「上げ」てしまいました。
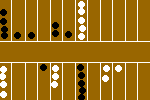 (4)上げられたら次の回は必ずそのコマを(ふりだしから)使わなければなりません。
(4)上げられたら次の回は必ずそのコマを(ふりだしから)使わなければなりません。
白のサイコロは「3」と「3」が出ました。上げられたコマを右下端(白のふりだし)から数えて3個目である3区画に
進めます。そして右下端のコマを3進めて4区画に置きました。もしサイの目と相手のコマ数との関係で進めない
場合は、上げられたコマは上がったままです。
次に黒が「6」と「6」が出ましたので、それぞれ2コマ、6ずつ進めています(上段)。
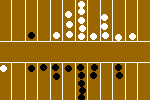 (5)回が進んだ状態です。白黒ほぼ同じように自分の色のコマを自分の陣地に引き寄せて
(5)回が進んだ状態です。白黒ほぼ同じように自分の色のコマを自分の陣地に引き寄せて
います。さて、次の白の番で「2」と「3」が出たとします。ここで左下端のコマを3使って上段10区画の黒を「上げ」たい
ところですが、それは得策ではありません。残りコマの数、ゴールへの近さなどから白が有利なのですから、
早くゴールインしたほうが良いのです。
この場合は「上げ」ることは考えないで、左下端のコマを5(2+3です)進めて、黒に上げられないように通過してしまった
方が良いでしょう。下手に黒を「上げ」てしまうと、黒の振り出しである右上端から黒が来ますので、白が一つである
2、3、5区画が上げられる危険を持ってきます。
このあたりの駆け引きが本双六の面白さでしょう。
※本双六の素晴らしいPCゲームフリーソフトを配布してくださるサイトがあります。
「源太企画」様です。ぜひご訪問、DLして下さいませ。
追い回し
白黒11個のコマを図のように配置し、時計回りに回って追いかけ追いつき、お尻からかじっていくゲームです。食うか食われるか白熱するゲーム性があります。
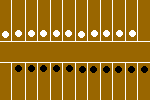 (1)まず双方が「乞い目」を決めます。これはコマを動かす権利が生じるサイの目です。
(1)まず双方が「乞い目」を決めます。これはコマを動かす権利が生じるサイの目です。
「1」と「6」は最初から双方共通の「乞い目」なので、それ以外の2〜5のうち、任意の2つの目をそれぞれが選びます。
双方で同じサイの目を重なって選択しても構いません。例えば白が「2」「5」、黒が「3」「5」を選んだとします。その場合、
白の乞い目は「1」「2」「5」「6」、黒の乞い目は「1」「3」「5」「6」の4種ずつです。
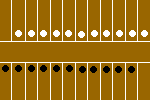 (2)サイコロ2つを振り、「乞い目」が出ると行列を1コマずつ前進させることが出来ます。
(2)サイコロ2つを振り、「乞い目」が出ると行列を1コマずつ前進させることが出来ます。
この図では白も黒も「乞い目」が1つ出て前進した後の状態を示しています。「乞い目」を出すと続けてもう一度サイコロを
振ることが出来ます。ここでは双方とも2度目の振りでは「乞い目」が出なかったこととします。
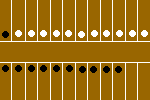 (3)白に「乞い目」が出ず、黒だけ「乞い目」が1つでましたので、黒が追いつきました。
(3)白に「乞い目」が出ず、黒だけ「乞い目」が1つでましたので、黒が追いつきました。
行列を動かすときは全体をずらすと大変なので、実際には最後尾のコマを最前列の前に動かすのです。
ここでも黒の2度目の振りでは「乞い目」が出なかったとします。
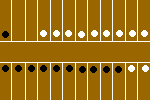 (4)サイコロを2つ振って、2つの目が両方とも「乞い目」であれば、2つ前進できます。
(4)サイコロを2つ振って、2つの目が両方とも「乞い目」であれば、2つ前進できます。
この例では追いつかれた白が「乞い目」2つを出して黒を振り切りました。
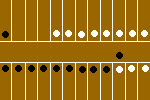 (5)追いついてから「乞い目」を出して前進すると、やがて相手のお尻に追いつきます。
(5)追いついてから「乞い目」を出して前進すると、やがて相手のお尻に追いつきます。
追いつけば相手のコマを「上げ」てしまうことができます。
ここでは(4)のあとの2度目の振りで「乞い目」が出て前進したことを示します。2度目でも「乞い目」でしたが、さらに
もう一度サイコロを振ることは出来ません。ここで黒と交代になります(2度目に「乞い目」が出ると3度目のサイコロを
振る権利が生じるというルールもあるようです。そうするとそこで「乞い目」が出れば、どんどん相手を「上げ」ていくことが
できますが、あまりに急激に勝負が進んでしまうような気がします)。
黒が不利な状況ですが、黒の番に回れば一気に追いつき追い上げることも可能です。
相手のコマ全てを「上げ」てしまえば勝ちです。
文献に見る双六
文献上で双六が初登場したのは、『日本書紀』 「
持統三年(689年)十二月丙辰、禁断雙六」 最初から禁令の対象でした。
律令でも禁止されており、『令義解(捕亡律)』を見ますと、賭博行為に対する罰則についての注釈として「謂博戯者、雙六樗蒲之属、即雖未決勝負、唯賭財者、皆定之」
と記載されています。何度も禁令が出ると言うことは、人々がいかにこのゲームに熱中していたかをよく表しています。
文学作品にも 双六に興じるシーンはたくさん登場します。
絵巻物『長谷雄草紙』には文人である紀長谷雄が羅生門で絶世の美女(実は合成人間?)を賭けて鬼と双六を打つシーンがメイン場面として登場します。
『枕草子』では「きよげなる男の双六を日一日うちて、なおあかぬにや、みじかき燈台に火をともして」と、時間を忘れて熱中している姿が描かれています。
『源氏物語』(常夏)では近江の君が侍女の五節の君と双六に興じる様が描かれています。内大臣(かつての頭中将)が外腹の娘である近江の君を引き取りましたが、この姫がなかなかに<おしとやか>でありません。仲良しのしゃれた女房と長々双六を楽しみ、相手に小さい目が出るようにもみ手をしながら「小賽小賽(小さい目小さい目)」と早口に祈る様が描かれています。
「簾高くおしはりて、五節の君とて、されたる若人のあると、雙六をぞ打ち給ふ。手をいとせちにおしもみて、せうさい、せうさいとこふ声ぞ、いと舌疾きや」
対戦相手である五節の君も負けじと
「この人も、はやけしきはやれる、御返しや、御返しや、と筒をひねりて、とみにも打ちいでず」
ただし、これは近江の君がやや品に欠けるとするシーンとして扱われており、貴族社会では碁などと比較して格落ちの遊びと考えられていたと推測できます。
近江の君は(若菜下)でも双六ファンで登場します。
「よろづの事につけてめであさみ、世の言種にて、明石の尼君とぞ幸い人にいひける。かの致仕の大殿の近江の君は、双六打つ時の言葉にも、明石の尼君、明石の尼君、とぞ
賽はこひける。」
世にラッキーパーソンとして有名な明石の尼君の名前を唱えて良い目を願ったのです。根っからの双六好きというイメージなのですね。
『大鏡』には双六が政治がらみで登場します。
村上帝の時、長男の広平親王は民部卿元方の孫でした。当然元方は親王が帝になることを願っています。しかし有力者である藤原師輔の娘安子も懐妊しました。安子が男皇子を産んだとなると師輔の孫として次の帝になることは明らかです。元方は、安子に女子が生まれることを祈りました。
庚申待ちの夜に公卿たちが双六に興じているとき、師輔が戯れに「ご懐妊中の御子が男子であられるなら重六よ出てこい!」と言って賽を振りますと、なんと6のぞろ目が出てしまいました! 師輔は大喜び。周りの公卿たちも驚いて「これは本当に男皇子が生まれるのではないか」と騒ぎました。しかし元方は真っ青です。
結局、安子は無事男皇子を出産し、皇太子になりました。元方はショックのあまり命を失いましたが成仏できず怨霊となって、「あの重六を見て、突然胸に釘を打ち込まれた気分がした」と言った・・・とのことです。
『大鏡』では、道長も双六ファンであったことが記されています。
「ひさしく雙六つかまつらで、いとさうざうしきにけふあそばせ」と道長が政敵である兄道隆を誘って「雙六の坪をめして」遊んだとされます。ついには「この御ばくやうは、うちたたせ給ぬれば、ふたところながらはだかにこしからませ給ひて、よなかあかつきまであそばす」ほど。裸で腰だけに衣類をまとい、夜明けまで徹夜で双六に興じたのです。今ならさしずめ徹夜麻雀といったところでしょうか。トップクラスの公卿も、肩の凝らないお遊びとして双六で遊んだ情景が目に浮かびます。
『源平盛衰記』には、有名な白河法皇の「天下三不如意」である「賀茂川の水、双六の賽、山法師、是ぞ
朕が心に随はぬ者」と遺されています。
『平治物語』には、ルールに係わる興味深い話が登場します。
「ぞろ目」の名称は、1のぞろ目なら「重一」、2のぞろ目なら「重二」などと呼びますが、3と4は「朱三」「朱四」と呼びます。これについて、当代一の物知りである信西が蘊蓄を傾けます。
「昔は重三、重四と言っていたが、唐の玄宗皇帝と楊貴妃が双六で遊んでいるときに、皇帝が重三の目を出そうとして「朕の思い通りになれば五位にしよう」と言って賽を振ったら重三の目が出た。続いて楊貴妃は重四を出そうとして「私の思い通りになれば一緒に五位にしましょう」と言ったところ、重四の目が出ました。二つの賽を五位に叙すこととして、五位のしるしとして何か・・・と考えれば五位の袍は赤衣と決まっています。それならばと、三、四の目に朱をさされました。それ以後、重三・重四を朱三・朱四と呼ぶようになった・・・」というのです。
なお、日本ではぞろ目を次のように呼び慣わします。
重一 (でっち)、重二(じうに)、朱三(しゅざん)、朱四(しゅし)、重五(でっく)、重六(ちょうろく)
時代は下がりますが『徒然草』には、国の運営を双六にたとえて名人の極意を語っています。
「勝とうとしてはダメ。負けないように打ちなさい。どの手を打てば早く負けることがないかを考えて、一目でも遅く負けるようにすべきである。」
HOME>装束の知識と着方>雅なお遊び>双六
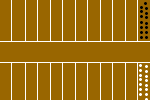 (1)2個のサイコロの目の数だけ2個のコマを前進させても良いし、目の合計数だけ1コマ
(1)2個のサイコロの目の数だけ2個のコマを前進させても良いし、目の合計数だけ1コマ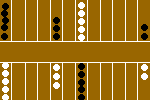
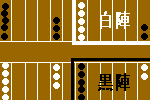
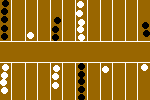 (2)白が先手になったとして、サイコロの目が「3」と「3」が出たとします。進行方向のルール
(2)白が先手になったとして、サイコロの目が「3」と「3」が出たとします。進行方向のルール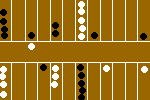 (3)次に黒の番。サイコロは「4」と「2」。まず右上端のコマを4前進させました。そして
(3)次に黒の番。サイコロは「4」と「2」。まず右上端のコマを4前進させました。そして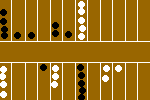 (4)上げられたら次の回は必ずそのコマを(ふりだしから)使わなければなりません。
(4)上げられたら次の回は必ずそのコマを(ふりだしから)使わなければなりません。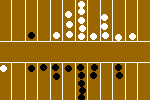 (5)回が進んだ状態です。白黒ほぼ同じように自分の色のコマを自分の陣地に引き寄せて
(5)回が進んだ状態です。白黒ほぼ同じように自分の色のコマを自分の陣地に引き寄せて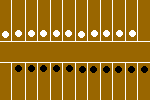 (1)まず双方が「乞い目」を決めます。これはコマを動かす権利が生じるサイの目です。
(1)まず双方が「乞い目」を決めます。これはコマを動かす権利が生じるサイの目です。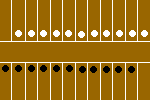 (2)サイコロ2つを振り、「乞い目」が出ると行列を1コマずつ前進させることが出来ます。
(2)サイコロ2つを振り、「乞い目」が出ると行列を1コマずつ前進させることが出来ます。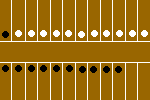 (3)白に「乞い目」が出ず、黒だけ「乞い目」が1つでましたので、黒が追いつきました。
(3)白に「乞い目」が出ず、黒だけ「乞い目」が1つでましたので、黒が追いつきました。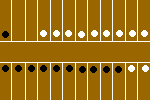 (4)サイコロを2つ振って、2つの目が両方とも「乞い目」であれば、2つ前進できます。
(4)サイコロを2つ振って、2つの目が両方とも「乞い目」であれば、2つ前進できます。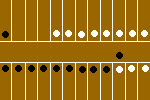 (5)追いついてから「乞い目」を出して前進すると、やがて相手のお尻に追いつきます。
(5)追いついてから「乞い目」を出して前進すると、やがて相手のお尻に追いつきます。