
冠位十二階を定めた聖徳太子の時代の服制は定かではありません。かつての1万円札で有名な伝「聖徳太子図像」は、奈良時代の服制による武官ものですから参考にはなりません。わずかに太子没後に制作された「天寿国繍帳」にある人物像が、当時の服制をたどるよすがとなります。
さらに天武朝になりますと、唐の影響を受けた服制がもたらされているようで、これは高松塚古墳壁画の図像に見ることができます。特徴的なのは前の打ち合わせが左前であることで、これはそれまでわが国・中国を問わず連綿と引き継がれてきた習慣でした。これは古墳から出土される埴輪でも確認されます。当時の服制は明確ではありません。官位制度は複雑になりましたが基本的には冠により区別され、たとえば藤原鎌足が「大織冠」の位を贈られたなど、服よりも冠に重点が置かれたようです。
 |
| 礼冠 |
奈良時代にはいると、唐の制度を受けて服制は刷新され、律令に基づく明確な法律「衣服令」(えぶくりょう)が定められました。この服制はほとんど唐の制度をまねたもので、これを受けた養老令(養老二年)では礼服(らいぶく)・朝服(ちょうぶく)・制服(せいぶく)が定められています。
礼服は重儀に用いられるもので、後には即位の大礼にのみ用いられ、明治天皇の父君孝明天皇の御即位までこれが用いられました。あまりに特殊であるのでこのHPでは礼服には触れませんが、完全に唐風のものです。
朝服は官吏の勤務服です。これが発展して束帯や衣冠になりました。文官は脇を縫った縫腋(ほうえき)の袍、武官は活動しやすいように腋を縫わない闕腋(けってき)の袍を用いました。冠は黒の羅で、五位以上は有文、六位以下は無文。文官は2本の纓(えい)を後ろに垂らし(垂纓)、武官は活動の便を図って上に巻き上げました(巻纓)。ここで興味深いのは武官が帯剣する際に剣を結ぶ帯を「倭織(しずおり)」と言い、わが国独自の原始的平織物を用いていることです。いかに服制が唐風になっても、武人の魂たる剣は和風でありたいという気持ちであったのでしょうか。この倭織の帯は後に「平緒」という飾りになりますが、紫だん(だんだら染め)などが多用されているのは、倭織の名残とも考えられます。朝服は後の袍と比較すると袖幅も細く、現代の洋服のように活動的でした。また袍を束ねる帯も「びじょう」が付いた現代そっくりの皮ベルトで、後の石帯よりも機能的ではありました。こうした動きやすい朝服が国風文化の興隆と共に次第に緩やかで幅広のシルエットに変化して袍になったのです。
制服は無位無冠の庶民が公事に従事する際の服で、朝服に似たものです。色は黄色とされましたが、この無位=黄色は明治まで引き継がれました。
こうして律令の定めは形を変えながらも原則として明治まで生きていました。装束については今日でも準拠していると言えるでしょう。
なお元正天皇の養老三年(719)二月三日、「初令天下百姓右襟」と定められ、今までの左前(左袵・さじん)が右前(右袵・うじん)となりました。このとき同時に官人に把笏を命じています。前年に遣唐使が帰国していますから、その報告によって世界最先端かつ国際ルールとしての唐の風俗にならったものでしょう。ちなみに左前は騎乗で矢を射るときに矢が服に当たることがないため、中国北方騎馬民族が愛用しました(さらに言えば、右前は刀を抜くとき鍔がひっかかりにくいという理由もあるそうです)。そのため、唐はそれまで自分たちも用いていた左前を蛮人風俗と忌み嫌い、右前に改めたと言われています。
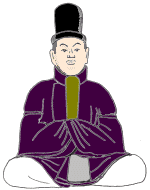 |
|
初期の頃は奈良時代のままでしたが、中期頃から国風文化の影響を受けてきます。すべてが幅広で、ゆったりとしたものになり、武官の服装もとても戦闘に向かない形式的なものになりました。藤原時代になりますと服色も現代と同じく黒・緋・縹の三色に集約されるなど、服制の面ではほぼ今日どおりになってきます。狩衣が公家階級の平常着になるのもこの頃です。重ね色目の定めもこの時代から起こってきます。
前代の平服が次代の礼服になるのは世の常ですが、直衣に冠を付けて宮中に参内できるようになったり、宮中でも束帯よりも(本来宿直装束の)衣冠が通常着になったり、なし崩し的に軽便な方式に切り替わってきました。これは律令政治の崩壊と期を一にしていることです。
「平安時代」と言っても400年間もあり、一口には語れません。ふつう簡単に「平安装束」というように言われますが、実は清少納言や紫式部の頃の装束の実相はよく判っていないのです。
摂関政治が衰え、院政時代が始まると武家の勢力が増大してきます。武家は公家よりも活動的な衣服を好み、また華美に走ることもなかったために、狩衣を公服として用いました。官位があればもちろん束帯も着用しましたが、公家ほど利用はしなかったようです。この風潮がこの時代以降続きます。たとえば水干は本来狩衣のように上げ頚で着用するものですが、この襟を内側に折り込んで今日の着物のように着たりすることもこの頃から始まります。裾も袴に着込めて活動しやすくしました。こうした装束の変化が直垂になり、肩衣になり、裃に変化していくことになるのです。
公家装束では鳥羽上皇の時代に画期的な変化が起こりました。剛装束(こわしょうぞく)の登場です。糊で固めた厚めの布、きわめて幅広のシルエット、現代のものとほぼ同じ装束です。これではとても一人では着用できなくなり、衣文道が生まれてくるのです。この動きは公家が政治の第一線から退き、華美に走り、活動的でなくなったことをも意味しています。特徴的なことの一つは冠です。纓(えい)はそれまで、冠の巾子(こじ)を締めた紐の名残で二本の布が後ろにだらりと垂れていました(武官は活動のため端を上に巻き上げていました)。ところが剛装束になると、纓は巾子の後ろから一度上がって下に垂れる形式になります。当然芯がなくてはこうはなりませんから、鯨のヒゲなどで形作り、そこに布を張って纓としました。武官はこれを巻くために、くるりとまん丸の巻纓(けんえい)になりました。院政時代はまださほど纓が高くありませんが、時代を経るに従って、立ち上がりが高くなります。ただし今日に至るまで、巾子よりも高くしないことを定法とします(天皇の立纓冠を除く)。
また、この頃から男女ともに下着に白い小袖を着るようになります。それまでは単が下着であったのです。
この時代には束帯はほとんど儀式のみに用いられるようになりました。院政では当然参内より院参が多くなるため、堅苦しい宮中と違って簡略化が目立ち、冠直衣が公服化しました。直衣の色(冬白・夏二藍など)や文様についての細かいきまりが生まれてくるのはそのせいかもしれません。今に伝わる「有職故実」のうち朝廷儀式に関すること以外は、この院政時代から鎌倉時代にかけて生まれ、室町時代に完成したものと言えるでしょう。
公家はまったく政治の実権を失い、儀式も自己目的となるに従って、細かな有職故実や衣紋道が成立しました。装束は前例踏襲を旨とするようになります。水干までもが公家の平常着に進出してしまうようになりました。武家は狩衣を公服とし、水干が改まった服、直垂が平常着になります。水干をVネックに着る方法を「垂頸(たりくび)」と言います(通常の着方は「上頸(あげくび)」)。この着方から直垂(ひたたれ)が生まれました。直垂が装束直系なのは現代の着物と異なって脇が縫われていないことで判ります。
京は戦乱がうち続いて荒廃し、公家も各地に散らばるなど、装束に凝るどころの時代ではありませんでした。天皇の袍の黄櫨染色の作出技術も失われ、それまで天皇の第二色であった「青色(青鳩色)」の袍が天皇の第一色になりました。応仁の乱から後の100年余りは公家文化が完全に途絶した期間であり、それ以前と以後では、かなり違った物になっていると言えます。江戸時代中期〜後期に「装束御再興」運動が起きるまでは、平安以来の故実から隔絶された時代が続きました。
織田信長は尊皇の意志が強く、有職故実家である山科家とのつながりもあって公事復興に力を示します。続く豊臣・徳川も政治的配慮もあってか尊皇を建て前として即位の大礼に資金を投じるなど、さまざまな面で装束の復興に力を注ぎました。しかし後年軽視された「寛永有職」という言葉があるように、当時の装束は古式とは似ても似つかず、能装束のような布で袍を作るなど、非常に混乱したものであったようです。
幕府は公家勢力の力を押さえるために「禁中並公家諸法度」を定め、衣服のことにまで制限を加えました。が、一方では享保以後には「ご再興」と称して乱れた服制を有職故実に則った形に戻そうという動きもありました。天皇の袍の黄櫨染色もこの頃から復興しています。
幕府の服制は第一位が束帯でしたが、これは将軍宣下などの重要公事にのみ用いられ、その他の場合は身分に応じて、直垂・狩衣・大文・布衣・素襖の階級に分かれていました。この時代になると狩衣は第一礼装とも呼べるクラスまで出世しています。また指貫も簡略化されて普通の袴のように下を切った「差袴」が多用されるようになり、狩衣のみならず衣冠の場合ですら利用されるようになりました。宮中の衣冠に於いてさえ一日と十五日のみ指貫(このころから奴袴・ぬばかまとも呼ばれるようになりました)で、それ以外は差袴が普通になってしまいました。
この時代の公家装束で特徴的なのは、袍や狩衣の襟(首上)が極端に低くなり、襟ぐりも大きくなって、下に着ている単や白小袖が襟から見えるようになったことと、冠に掛け緒を使うようになったことです。冠は本来は簪で巾子に入れた髪を突き刺して留めていたのですが、この時代は月代(さかやき)を剃るようになって髪が減ったためにこれができなくなり、掛け緒で固定する必要が生じたのです。これにより冠や烏帽子は小型化し、頭にちょこんと乗っているだけのようなものになりました。
女房装束でも、宮中女官が白小袖に緋袴が通常服となり、袴の緒を肩に掛ける「大腰姿」という変わった着方もされました。また裳には「掛け帯」というものを肩から前に掛けて結ぶ、平安時代にはなかったものも用いられ、さらに髪型も(もともとは京都吉原習俗の)「おすべらかし」という大仰な形が取り入れられました。
こうした故実にない装束は元和6(1620)年の徳川和子入内から少しずつ是正され、天保15(1844)年、のちの孝明天皇御元服の「御再興」で改められましたが、女房の髪型が「おすべらかし」であるように、装束も多くの面で平安時代とは懸け離れたものになっています。。今日目にする装束のほとんどがこの頃の形式のものなのです。
公家は各家の家格や職掌が世襲化し、その家独自の文様などが生まれました。袍でも大臣になるまでは輪無唐草や轡唐草などの通用文でしたが、大臣任官の後は各家独自の文を織りだして用いるといったことが行われるようになりました。万事旧習を墨守することが尊重された時代だったのです。このころの公家の経済的困窮は著しく、装束も満足に整えることは困難で貸衣裳に頼ることもあったようです。京には「若狭屋」「鍵屋」などの貸衣裳屋があり、黒袍・縹袍装束一式を百疋、赤袍装束一式二百疋で貸し付け、その他供奉の随身装束まで一式を貸していた言う話が伝わっています。
王政復古に伴い、当初は和風重視の風潮がありました。明治天皇即位の大礼に礼服でなく束帯を用いたのもこのためです。慶應3年(1867)年12月に万機ご一新の告諭がなされましたが、当時は混乱期で服制どころではなく、「冠以下官服類追々制度立てさせらるべく候得共、まずそれまでの処、従来のまゝ着用これあるべき旨、仰出され候事」との布令がなされました。西欧嗜好の強い西園寺公望が便利だからと勝手に洋服で参内して物議を醸したのもこのころです。
しかし当時の極端な近代化の流れにおいては、あまりに形式化した装束はもはや時代にそぐわないものとされてしまいます。
明治4年(1871年)の初夏、宮中において服制改革についての会議が開かれました。太政大臣三条実美の「今日の議事内容は我が国の風俗についての大改革であり、主上のご身辺に関することでもあるので充分なご審議をいただきたい。服装は大礼の根本である。開化進取の方針に従い、この際、洋服に一定然るべしという提案が出ており、これに対しての意見を承りたい」との挨拶で白熱の議論はスタート。
洋服推進派の後藤象二郎は「洋服は起居進退があきらかに便利ではないか。この際、旧来の因循姑息を退け、世界を渡り歩く気概を養うためにも大英断をもって洋服を採用すべし」と主張しましたが、「便宜上の理由だけで長い伝統の服装を一気に改めようとするのは言語道断である。外国人に製作を依頼するのは外交上も風下に立つことになり、また国費が海外に流出することにもなる。主上の御衣服も変更申し上げねばならないが、なんとも畏れ多いことである。なんでも外国を模倣すれば良いとする考え方は承服できない」という反対意見も出ました。
これに対して副島種臣は「利便性、外交上の得失、経済上の損失という論議ばかりだが、これは失礼ながら枝葉末節の論議である。かつて趙の武霊王が胡の国を制するに胡服を用い大勝したという故事がある。わが国の天業が正義をもって世界に臨むことであることを考えれば、この武霊王の例に倣い、この際洋服を用いるべきである」と話をまとめ、さらに参議西郷隆盛が「副島どんの『胡服をして胡を制す』の意見に賛成でごわす」と重みのある発言。ここに廟議は決しました。まず明治4年8月9日、官吏および華士族に対して「散髪、脱刀及び洋服、勝手たるべし」という御沙汰があり、明治4年9月4日に「服制を改むるの勅諭」が発せられました。
「朕惟うに、風俗なる者移換以って時の宜しきに随い、国体なる者不抜以って其勢を制す、今衣冠の制、中古唐制に模倣せしより流れて軟弱の風をなす、朕これをはなはだなげく、それ神州武をもって治むるやもとより久し、天子親(みずか)らこれが元帥となり、衆庶以て其風を仰ぐ、神武創業、神功征韓の如き決て今日の風姿にあらず、豈に一日も軟弱以て天下に示すべけんや、朕今断然その服制を更(あらた)め、その風俗を一新し、祖宗以来尚武の国体を立たんと欲す、汝近臣それ朕が意を体せよ。」
かなり衣冠に厳しい表現ですが、富国強兵には衣冠は向かない、ということは確かだったでしょう。
ちなみにお歯黒・眉墨は明治3年2月5日に「華族自今元服の輩、歯を染め、眉を掃き候儀、停止仰出され候事」(太政官日誌)、明治6年3月3日には「皇太后宮、皇后宮、御黛(まゆずみ)、御鉄漿(おはぐろ)廃され候」(宮内省仰出)と廃止されています。
さらに明治5年11月12日太政官布告第339号「大礼服及通常礼服ヲ定メ衣冠ヲ祭服ト為シ直垂狩衣上下等ヲ廃ス」が布告され、「爾今禮服には洋服を採用す」「衣冠を祭服とす」と定められ、翌年狩衣を衣冠の代用服とせられました。ここに装束は公事服としての役割を洋服に譲り、神事専用服へと変化するのです。しかし皇室においては儀式には束帯以下各種装束が用いられ、現在に至っています。
(余談:明治百年に当たる昭和47年に全日本洋服協同組合連合会が、太政官布告の出た11月12日を「洋服記念日」と定めました。これについて記載したWebサイトの多くは太政官布告を「330号」としていますが、これはどこかで間違ったままコピーされ続けているのでしょう。正しくは339号です。この布告は昭和29年法律第203号「内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律」で廃止されるまで効力を持っていました。)
今日、神職以外で装束を着用するのは皇室関係と国技相撲関係者くらいなものでしょう。後者は行司が土俵で神事を行う際に用いるのですが、白狩衣(浄衣)に冠を付けるなど、いささか有職故実にそぐわないものです。
一方、さすがに皇室は戦前からの装束の伝統を受け継いでいます。天皇の黄櫨染御束帯や白色小葵文の御引直衣、皇太子の黄丹の袍、親王の黒色雲鶴文の袍など、まったく旧習を守ったものです。ただし天皇の冠「立纓冠」の纓が直立しているのは明治以降のもので、現在では束帯は即位・御成婚などの重儀にのみ着用され、通常の神事などでは衣冠が正式礼装とされています。
| 地位 | 種別 | 冠 | 上衣 | 袴 | 用途 |
| 天皇 | 御束帯 | 菊花文立纓冠 | 黄櫨染桐竹鳳凰文 裏二藍平絹 |
表袴・白浮織かに霰文 | 宮中祭祀、各種重儀 |
| 御引直衣 | 同上 | 白固織小葵文 裏二藍平絹 |
紅固織長袴小葵文 | 神宮・神武天皇陵への勅使発遣の儀 | |
| 御直衣(冬) | 同上 | 同上 | 紅精好切袴 | 勅使発遣、神武天皇祭御神楽の儀他 | |
| 御直衣(夏) | 同上 | 二藍穀織三重襷文 | 同上 | 同上 | |
| 御小直衣 | 御金巾子冠 | 直衣と同じ | 直衣と同じ | 節折、神社奉納御霊代御覧 | |
| 皇太子 | 束帯 | 菊花文垂纓 | 黄丹かに鴛鴦文 裏黄平絹 |
表袴・白浮織かに霰文 | 宮中祭祀、各種重儀 |
| 単衣冠 | 同上 | 同上 | 指貫紫浮織かに霰文(冬) | 宮中三殿期日報告の儀他 | |
| 直衣(冬) | 同上 | 白固織小中葵文 裏二藍平絹 |
指貫紫浮織かに霰文 | 祭祀御作法習礼 | |
| 直衣(夏) | 同上 | 二藍穀織三重襷文 | 二藍生浮織雲立涌文 | 同上 | |
| 皇族 | 束帯 | 菱繁文 | 黒雲鶴文 裏黒平絹 |
表袴・白浮織かに霰文 | 大礼、紫宸殿の儀、御成年式 |
| 単衣冠 | 同上 | 同上 | 指貫紫固織雲立涌文 | 宮中三殿期日報告の儀他 | |
| 小直衣 | 烏帽子掛緒紫 | 白固織鶴ノ丸文 裏紫平絹 |
指貫紫固織雲立涌文 | 御作法習礼 | |
| 掌典官 (旧勅任) |
単衣冠 | 小菱繁文 | 黒輪無唐草文 | 指貫紫固織八藤丸文 | 大礼、勅使、重儀供奉 |
| (旧奏任) | 同上 | 同上 | 緋輪無唐草文 | 指貫紫無文平絹 | 同上(随員) |
| (旧判任) | 同上 | 遠文 | 縹無文 | 指貫浅黄無文平絹 | 同上(随員補) |
| 出仕 | 雑色 | 平礼烏帽子 | 萌黄布狩衣 | 指貫萌黄布無文 | 同上(雑色) |
色彩と文様のイメージ(明治以降近代の制度)
束帯(判任官には束帯の制なし)
| 天皇 | 皇太子 | 親王 | 勅任官 | 奏任官 | |
| 袍 |  |
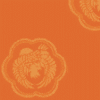 |
 |
 |
 |
| 表袴 |  |
 |
 |
 |
衣冠(天皇は衣冠がないため御引直衣)
| 天皇 | 皇太子 | 親王 | 勅任官 | 奏任官 | 判任官 | |
| 袍 |  |
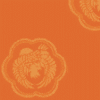 |
 |
 |
 |
|
| 指貫 袴 |
 |
 |
 |
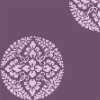 |
現在の神職の服制は昭和21年6月に神社本庁が定めた「神職の祭祀服装に関する規程」が基本になっています。
装束は(1)正装=衣冠、(2)礼装=斎服、(3)常装=狩衣・浄衣に分類され、正装は大祭および天皇陛下の御参拝に際して着用、礼装は中祭、常装は小祭および諸式に用いると定められました。
神職と神社に関する豆知識はこちらを参照してください。
神職の祭祀服装に関する規程 (表記の一部を現代仮名遣いに読み替え)
第一条 神職の祭祀服装は、正装、礼装およぴ常装の三種とし、その服制は別表による。
第ニ条 正装は、左の場合に用いる。
一 大祭の場合
ニ 天皇 三后 皇太子または皇大孫御参拝の場合
第三条 礼装は、中祭の場合に用いる。
第四条 常装は、小祭及び神社において行う恒例式の場合に用いる。
第五条 当分のあいだ、礼装をもって正装に代えることができる。
神社において由緒ある式年祭その他これに類する厳儀奉仕上、特に必要のあるときは、その神社の宮司に限り、統理の承認を受けて、その当日一等級上位の正装を用いることができる。
当該神社に古例がある場合は、その古例に従うことができる。
神事又は礼典の場合には、斎服、狩衣、常服、浄衣その他の祭祀に適する服装を用いることができる。
附則
本規程は昭和ニ十一年六月一日より之を施行する
附則(昭和三十九年六月十日規程第ニ号)
本規程は、昭和三十九年七月一日より之を施行する。
ニ級上正装衣冠およぴ袿袴の袴は、昭和三十九年五月末日までに昇級したものについては、
当分のあいだ従前の「紫固織裏同色平絹無文緯白」を用いることができる。
正装(衣冠)
| 身分等級 | 特級 | 一級 | 二級上 | 二級 | 三級 | 四級 |
| 袍の色 |  |
 |
 |
 |
||
| 袍の文 | 輪無唐草 | 輪無唐草 | 輪無唐草 | 輪無唐草 | 無文 | 無文 |
| 指貫・ 差袴の色 |
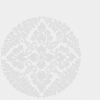 |
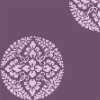 |
 |
|||
| 指貫の文 | 八藤丸文 大文白 |
八藤丸文 紫緯白 |
八藤丸文 紫緯共 |
無文 紫平絹 |
無文 浅葱平絹 |
無文 浅葱平絹 |
| 冠 | 垂纓繁文 | 垂纓繁文 | 垂纓繁文 | 垂纓繁文 | 垂纓遠文 | 垂纓遠文 |
袍は旧官員の制度に準じています。特級・一級は勅任官の黒袍、二級上・二級は奏任官の赤袍、三級・四級は判任官の縹袍です。ただし縹は古制にならい、「緑袍」と称して、実際にグリーンがかった縹色になっています。一時期、二級上の袍色を藤色にしようという検討もなされましたが、故実にない色目であり品位にも欠けると判断されて見送られたようです。
指貫も官員の制度に準拠していますが、本来は赤袍の指貫は紫平絹です。二級上の指貫・差袴は当初の規定によれば緯白紫固織(無文)でした。その後昭和39年に八藤丸文(規則上は八藤文も地と同じ紫)を認められています。一級の袴は緯糸が白であるため全体の色が紫より白ばんでいます。一方、二級上の袴は緯糸が薄紫のため、文が薄紫、全体が赤紫の色になっています。この色目は有職故実には見あたらないものです。特級の白地白八藤は画面上グレー処理してあります。特級の八藤丸文は一回り大きい大文です。三〜四級の浅葱は、通常は上記のような色ですが、作業の多い若手の袴としては汚れやすいと言う実情からか、縹に近い濃いめのブルーを着用することもあるようです。規程では色見本まではないため、そのあたりは弾力的に運用されています。
正装は大祭(例祭・祈年祭・新嘗祭・遷座祭など)、天皇陛下の御参拝に際して着用します。
礼装(斎服)
各階級同じで、冠は垂纓遠文、白絹の裏なしの袍、白絹の差袴となります。
礼装は中祭(歳旦歳・紀元祭・天長祭など)に着用します。
常装(狩衣・浄衣)
狩衣は織地、色(禁色を除く)、文はまったく自由で三・四級が裏を付けられないこと、袖括りの緒が二級以上が薄平、三級以下が左右縒であること以外は各階級共通です。立烏帽子もまた同じです。ただし、指貫(または差袴)は正服に準じます。
浄衣は白狩衣白差袴で各階級同じです。
常装は小祭(大中祭以外の祭祀及び大祓式などの恒例式)、日常の奉仕に着用します。
その他の装束(その他の祭祀に適する服装)
現在、地鎮祭などで出張する神職が用いるのは「格衣(かくえ)」が多いようです。これは直垂の上衣の脇を縫ったもので、羽織のように簡単に着ることができるので多用されています。白小袖の上に羽織り、差袴着用、立烏帽子をかぶります。
また闕腋袍のような白い袍である「明衣(みょうえ)」や、袍の代わりに小直衣を用いることもあるようです。
女子神職の服制については「現代女房装束の基礎知識」をご参照ください。